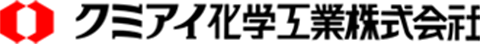持続可能な農業に貢献し、クミアイ化学は次のフェーズへ
代表取締役社長

研究員としてスタートし、海外事業で積み上げたキャリア
2024年11月に代表取締役社長に就任した私は、大学時代に農学を専攻して以来、長きにわたり食と農業に携わってまいりました。1989年のクミアイ化学入社後は、生物科学研究所に配属され、除草剤の研究員としてキャリアをスタート。1994年に国外部(現:海外営業本部)へ異動し、2002年から2009年に欧州に7年間駐在しました。
帰国後は海外営業や経営企画などを経て、現在に至ります。通算で26年間と海外業務のキャリアが長いのですが、当社は今、海外売上が単体で約7割を占めます。事業拡大の礎を築いた一員である自負は、トップとなった今、私にとって大きな原動力となっています。
2026年度を最終年度とする現在進行中の中期経営計画は、前社長の高木と共に練り上げました。この路線を引き継ぐのが私の基本方針ですが、加えて新体制では三つの方針を掲げています。「強靱な企業体質への変革」「サステナビリティ経営の推進による企業価値の向上」「全てのステークホルダーの幸せの追求」です。
事業環境の変化に左右されない盤石な企業体質に変える
一つ目の「強靱な企業体質への変革」は、経営基盤の強化にあたります。既にクミアイ化学は強固な事業基盤を築いており、多少の外圧に動じることはありません。
しかし一方で、企業というものは“いつ潰れてもおかしくない”と、私は常々意識しています。そして、当社の農薬を中心とした事業活動は、継続ができなければ日本および世界中の農業、食料供給に甚大な影響を及ぼします。持続的な事業活動の礎になるのは、利益の創出です。
企業にとっての利益は従業員の雇用、社会貢献などにつながる、人間にとっての“水”のような存在。人は水がなければ生きていけませんが、水を飲むために生きているわけではありません。事業を通じた社会貢献と利益創出の両軸で、企業体質の変革を目指したいと考えています。
具体的に注力するのは、「意識・組織改革による収益力の強化」「顧客のニーズ・ウォンツを先取りした製品・技術開発による新たな価値の創出」「人財戦略ビジョンの実現と人財育成」「DXの推進/デジタル化の実践」です。当社が継続して成長するためには、新たな価値の創出が必要ですが、当社の生命線は世の中にない製品を開発すること。農薬の有効成分となる新規化合物を生み出し、農薬という製品に形を変えるまでの、一連の研究・開発活動から農薬登録後の普及・販売活動までが価値創造の源泉となりますので、それに付随する革新的な技術開発や人財育成、DXによる研究や生産の効率化に努めてまいります。未来の顧客ニーズを予測し、製品開発にまい進する考えは、化成品事業でも同様です。社会的需要の伸長が予測される半導体をはじめとする電子材料分野を成長分野と捉え、積極的な事業展開を図っていきます。「収益力の強化」「新たな価値の創出」「人財育成」「DXの推進」に注力することで、事業環境の変化に左右されない企業体質をつくりあげていきます。
二つ目の「サステナビリティ経営の推進による企業価値の向上」では、グループ会社を含む社会的価値の向上を目指します。当社は2021年にサステナビリティ基本方針を策定するとともに、サステナビリティ推進委員会を設置し、主に脱炭素社会の実現、循環経済への移行に向けた取り組みを強化してきました。
脱炭素の分野では、「2030年度までに2019年度比で30%のGHG排出量削減」「2048年度までのカーボンニュートラル実現」という目標を掲げています。政府が示す2050年より2年前倒しさせたのは、2048年が当社の創立100年目にあたるからです。特にCO₂排出量が多い工場と研究所では、電力の再生可能エネルギー等由来のCO₂フリー電力への切り替え、重油からGHG排出量の少ない燃料への切り替えを進めており、現時点で2030年度の数値目標は達成のめどが立っております。
同時に、社会課題への取り組みとしてダイバーシティ&インクルージョン(D&I)、ワークライフバランス、健康経営®においてはKPIを設定し、アクションプランに沿った施策を推進中です。
また、「人権尊重」をサステナビリティ経営の基盤と考え、「人権に関する基本方針」「人権デュー・ディリジェンスのためのガイドライン」を制定し、人権の尊重を推進しており、ガイドラインに基づきサプライヤーへのアンケートを実施するなど、継続して人権課題にも取り組んでいます。
こうした取り組みを通じ、環境や社会へ貢献することで、企業価値を向上させたいと考えています。
- 「 健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
一人一人の“志” が成果を生みステークホルダーの幸せにつながる
三つ目の「全てのステークホルダーの幸せの追求」ですが、前社長の高木が社長就任時に方針として掲げた「『夢』と『幸せの三角形』」が現在の中期経営計画のスローガンとなっており、当社およびグループ会社の役職員の中に、このコンセプトが浸透しております。私はこのコンセプトに、「志」という言葉を加えたいと思います。社員一人一人が夢と希望と志を抱き仕事に打ち込めば、高い成果が生まれ、会社が強くなる。それが従業員やその家族、取引先や株主にとってプラスになり、やがて全てのステークホルダーが幸せになる。こうした好循環を育めるよう、この理念をグループ全体に共有していくつもりです。
2024年度の連結売上高は1,610億円、前期から4,700万円の増となり、14年連続の増収を達成しました。一方、営業利益は114億円で、前期から大幅な減益となり、厳しい結果と受けとめています。世界的な農薬市場における在庫圧縮の動きや競合剤の価格下落による影響を受け、販売が計画通りに進まなかったことに加え、これまで追い風となっていた円安、農作物の価格上昇と需要増加などが踊り場を迎えたことがマクロな要因と捉えています。
そして事業に目を向けると、海外事業の中核となるアクシーブ®(有効成分名:ピロキサスルホン)の事業環境が変化したことも、要因の一つです。畑作用除草剤のアクシーブ®は、ダイズ、トウモロコシ、コムギ、サトウキビなどの栽培において、既存の除草剤への抵抗性を持った雑草に対しても高い効果を発揮することから、2011年の販売開始以来、着実に成長してきました。現在アクシーブ®は、世界25カ国(2025年3月末現在)で農薬登録されています。このアクシーブ®は、2022年に物質特許の有効期間が満了しました。最大の防御である物質特許の失効後、ジェネリック品や当社特許侵害品が市場に流入し、安価で普及し始めたため、当社もアクシーブ®市場を維持するために販売価格対応をせざるを得ず、結果として減益につながったと考えています。
アクシーブ®の特許侵害対策を推進しつつコストダウンによるシェア拡大も射程に
こうした状況を打開すべく、現在当社では特許権の侵害が認められた場合には、断固たる対応を行うという方針のもと、法対応を進めております。
アクシーブ®は物質特許こそ失効したものの、混合剤開発による特許、製造法や中間体に関する特許などはいまだ有効です。製造プロセス全体で知的財産権を行使することで、特許侵害品への対策が可能になります。
すでにオーストラリアでは、ピロキサスルホン含有製品の販売会社に対し、特許権侵害訴訟を進め、当社の勝訴的和解により終結した事案もあります。こうした活動の継続により、オーストラリアではオリジナル品であるアクシーブ®の販売を回復させていける見込みです。
ただし中長期的には販売価格対応を実施する状況が続くため、かつての急成長から緩やかな成長へとシフトする可能性があるのは事実です。一方で、販売価格対応によりアクシーブ®の新規ユーザーの獲得にもつながっております。悲観的に捉えるのでなく、商機として積極的に戦略を策定することで、アクシーブ®のさらなる普及を図りたいと考えています。
エフィーダ®の海外展開を本格化し国内では新製品を着実に開発
同時に、業績改善に向けた製品ポートフォリオの強化も必要です。当社は他にも有力な製品群を備えています。国内の水稲用除草剤分野では、混合剤化により多様な雑草を長期間抑制できる一発処理剤の分野が重要ですが、当社は初・中期一発処理除草剤分野で4年連続トップシェアを維持してきました。この分野で力を発揮しているのがエフィーダ®です。国内で浸透したエフィーダ®を、本格的に海外へと展開することで、新たな中核事業を育むことができると考えております。
エフィーダ®の潜在能力を最大化できる市場の一つが、世界有数のムギ類生産地域である欧州です。現在、畑作用除草剤としての事業展開を念頭に、欧州での農薬登録申請を行っております。また、米国ではValent社との提携により、同国向け水稲用除草剤の共同開発をスタートさせました。
2025年1月には、国内にて新たな水稲用殺菌剤としてリガード®が農薬登録され、2026年に販売を開始する予定です。自社開発殺ダニ剤のバネンタ®の開発を進めており、登録後の上市に向けて準備を進めております。国内事業では、他社開発剤の導入による新製品、既存剤の組み合わせによる混合剤など、自社独自開発以外の手法も有効になります。多角的なアプローチを進めながらも、長期的には当社の優れた研究開発力を駆使し、アクシーブ®に匹敵するような新規化合物の開発を目指すことで、強力な製品ラインナップをそろえていきたいと思います。
化成品事業においては、塩素化事業が中国との競争で苦戦を強いられ、売上に大きく影響しました。知財戦略が通用しづらい川上の化成品領域は、農薬とは異なり価格競争の比重が大きく、市況の悪化にも影響を受けやすいことが背景にあります。その一方で、樹脂原料となるビスマレイミド類(BMI類)は、需要が高まる半導体の基盤にも用いられることから、業績が好調です。化成品事業トータルとしては増収増益となっており、今後も半導体需要の増加を背景として、好調の波は続くと考えています。
これらの成果は主にグループ会社によるものですが、クミアイ化学本体でも化成品事業を強化してまいります。2023年に稼働を開始した化学研究所ShIP(Shimizu Innovation Park)には、新素材開発研究室を新設し、全く新しい素材の研究や既存製品の用途開発を行っています。同研究室にはグループ会社の研究員も結集しており、さまざまな領域の知見を融合させることに努めています。高度な研究力を武器に、化成品事業を農薬に続く第2の柱へと成長させることを目指します。
前中期経営計画の期間にあたる2021〜23年度は、新たな可能性へのチャレンジと位置付け、研究開発力の強化、生産コスト低減に向けた大型の成長投資、事業拡大に向けた国内外でのM&A、サステナビリティ経営に関する取り組みなどを推進してきました。これらを継承する形で、現在の中期経営計画(2024〜26年度)では、7つの重要方針を掲げています。「持続可能な農業への貢献/高品質な製品・サービスの安定供給」「気候変動・環境負荷の低減」「研究開発力の強化」「事業領域の拡大と新規事業の推進」「人財の育成/人的資本の考え方をベースにした人財戦略」「コーポレートガバナンスの高度化」「DX の推進/デジタル化の実践」です。それぞれの方針のもとで新たな施策を試みており、徐々に成果が表れている領域もあります。
持続可能な農業への貢献/高品質な製品・サービスの安定供給
人口増や食生活の変化による食料需要の増加、気候変動や地政学リスクなどにより、世界の農業はさまざまな課題に直面しています。単位面積当たりの収穫量を高め、安全・安心な食料生産に不可欠な農薬を提供することは、農薬事業に従事する当社の責務です。先述した特許侵害対策、国内製品の海外展開などは、安定的な食料生産につながり、サステナブルな社会の実現に貢献すると考えています。
また、特に国内では、生産者の高齢化や人手不足が深刻です。作付面積が減少する中、将来的には農業生産法人が増加すると予想され、現場では農作業の効率化が求められています。当社は現在、スマート農業に貢献する自社開発製剤である豆つぶ®剤を販売し、ドローンでの農薬散布を実現するなど、生産者の労力軽減の支援に努めています。
このように、当社が有する技術やネットワークの力で、持続可能な農業の構築を支えていきます。
農林水産省は「みどりの食料システム戦略」を策定し、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立を、イノベーションで実現することを掲げています。設定されたKPIの中でも当社事業に直結するのが、化学農薬使用量を2050年までにリスク換算で50%低減する目標です。農薬業界にとっては逆境にも見られますが、より効果が高く、安全で、環境負荷が低い農薬の開発は、創立当初からの長年にわたる当社の研究開発方針でもあります。当社方針の方向性と政策の方針に相反する点はないため、私はこれを危機ではなく、ビジネスチャンスと捉えています。
例えば、かつて水稲用除草剤は、1haあたり3kgもの有効成分の散布が必要でしたが、現在当社の製品ではわずか30gのものもあります。こうした農薬の少量化は、輸送プロセスのCO₂削減にもつながります。また、農薬登録における国際的な安全性評価基準への対応は、年々ニーズが高まっておりますが、当社では2021年に生物科学研究所の安全性評価研究棟を建設するなど、研究環境の強化を図ってきました。
さらに、環境負荷がより小さく、化学農薬を補完し、さまざまなニーズに対応できる微生物農薬やバイオスティミュラントの開発も推進しております。このような環境負荷の低減や安全性の確保に向けた取り組みについては、今後も徹底してまいります。
前中期経営計画では、先述した化学研究所ShIPの設置に取り組み、創薬研究センター、製剤技術研究センター、プロセス化学研究センターの3拠点を統合することで、化学系の研究機能を強化しました。一方で、新たな化合物の研究開発においては、農薬としての実装を評価する生物系の機能も欠かせません。現中期経営計画では、生物科学研究所への投資を強化しております。その一環として、新たな研究棟が2027年に完成予定です。化学系と生物系の両輪がそろうことで、新農薬の創製はさらに加速するでしょう。
また、社外の研究機関とも積極的に連携するとともに、AIを活用した独自の創薬手法の確立に向けた取り組みを推進するなど、基盤技術の整備も進めております。
農薬及び農業関連事業、化成品事業を主軸としながらも、当社では周辺分野への事業展開も進めています。主な起点はM&Aであり、前中期経営計画ではシンガポールのAsiatic Agricultural Industries(AAI)社の連結子会社化、福島県のアグリ・コア社および宮城県のGRA社の株式取得を実現しました。現在、AAI社によるアジア・アフリカへの販路拡大、アグリ・コア社によるIT技術を用いたワサビ生産、GRA社によるスマート農業でのイチゴ栽培など、各社がグループの事業領域拡大のために尽力しています。今後はテクノロジー活用などで当社と連携するなど、相乗効果の創出に挑戦していきたいと考えております。
人財の育成/人的資本の考え方をベースにした人財戦略
当社および当社グループの持続的な発展のためには、人財の確保・育成が欠かせません。現在、「努力」を後押しする環境を整備し、「成果」を通じて達成感を得られるような仕組み作りを目指して、人事評価・報酬制度の抜本的な見直しを進めており、2026年度からの運用開始を予定しております。改革の背景にあったのは、30年もの長い間にわたり硬直していた人事制度です。成果を上げた従業員が十分に評価される仕組みを整えながら、複合的な昇給制度、地域限定社員制度などを導入し、キャリアの多様性も確保することで、従業員と会社のエンゲージメントを向上させます。
コンプライアンスやリスク管理は、昨今ますます重要性が増しています。当社は「人権デュー・ディリジェンスのためのガイドライン」を制定するとともに、2023年には健全なグローバル社会を築く「国連グローバル・コンパクト」に署名し、人権や労働面での取り組みを強化し続けています。
また、ダイバーシティ&インクルージョンの推進に向け、全国の従業員に公募をかけて「ダイバーシティ推進ワーキンググループ」を設置しました。誰もが働きやすい会社を目指し、現状の課題と目指す姿を取りまとめるとともに、経営に対する提言を現場から収集してもらいました。2024年には提言内容をベースにした管理職向けダイバーシティ研修を実施するなど、現在取り組みを強化中です。
DXの推進/デジタル化の実践に向け、2024年5月に情報システム統括部を設置しました。DXの推進は現代の企業存続に欠かせませんが、形骸化したDXは意味をなしません。その本質の理解を促進すべく、IT領域に関心のある社員を全国から募り、情報システム統括部で4カ月間の基礎研修を実施します。研修の目的は、個人のITスキルの向上を図ることと、本社のノウハウを事業所と共有し、現場レベルでDXを推進することです。ボトムアップ式の取り組みを進め、優れた知見や成功例が展開されれば、グループ全体としての生産性向上も実現できると考えています。
100年企業としてのあるべき姿に向かい各種施策を完遂する
一連の取り組みを通じて当社グループがまず目指すのは、現在の中期経営計画で掲げた、2026年度における売上1,850億円、営業利益160億円という目標を達成し、投資家の皆様にも利益を還元することです。同時に、当社グループは100年企業としてのあるべき姿を「独自技術で豊かなくらしを支え、自然と調和した社会の持続的発展に貢献するフレキシブルで存在感のある企業グループ」と設定しています。現在の中期経営計画はその重要な一歩です。長期的な成長を常に視野に入れながら、計画達成に向けた各施策を遂行したいと考えています。
私は社長就任時の所信表明で、全役職員に対して三つのお願いを伝えました。
一つ目は、健全な危機意識を持つことです。
当社の成長を支えてきたアクシーブ®ですが、今後もその右肩上がりの成長を享受できるわけではありません。むしろ事業環境の変化を見据え、健全な危機意識を抱きながら、それぞれが各事業に全力であたることが重要です。
二つ目は、変化を恐れないこと。組織は、自然界のメカニズムと同様に、変化に適応したものだけが生き残ります。ビジネスにおいても変化を恐れてはなりません。逆に、変わらないこと、変われなくなることを恐れるべきだと思います。過去の成功体験に固執するのではなく、むしろそれらを疑い、新しいことに果敢に挑戦を続けるべきと、伝えました。
そして三つ目は、結果にこだわることです。努力の質と量、方向性が正しければ、必ず結果は伴います。私はプロセスにおける努力や苦労を理解はしますが、これのみを評価することはありません。常に貪欲に成果を求めながら、時に成果とは何かと問い直す。こうしたマインドを持って仕事にあたってほしいと、皆に強調しました。
これら三つのお願いは、私の個人的な価値観にも基づきます。私自身が陣頭に立ち、リーダーシップを発揮しながらこうした姿勢を実践することで、会社を牽引したいと思っています。
クミアイ化学の価値創造が未来世代へと受け継がれるために
コア事業である農薬を中心に、世界の食を支える当社の事業は、持続的に社会へ価値を提供できると確信しています。新規化合物の合成・探索をはじめとする研究開発は時間を要することからも、ステークホルダーの皆様の長期的な支援が欠かせません。
一方、当社の財務状況に目を向けると、ROE(自己資本利益率)は高水準にもかかわらず、将来の成長への期待値を示す PER(株価収益率)は低い傾向にあります。この傾向は業界全体でも見られることから、私は要因の一つを農薬に対するネガティブなイメージと分析しています。
一般消費者を含む幅広いステークホルダーの皆様に、当社事業の重要性や成長ビジョンを共有するためには、農薬の必要性や高い安全性を周知することが必要です。これまでも当社は学校出前授業をはじめ啓発活動に取り組んできましたが、2024年には新たに高校生を対象とした「『食料生産』について考えよう〜もし、農薬が世界からなくなったらどうなる?〜」という食育プログラムをスタートしました。農薬をテーマにしたディスカッションを行い、レポートを作成するプログラムです。参加した高校生は、自主的なリサーチやインタビューを実施し、正確な情報に基づいた極めて高度なレポートを提出してくれました。未来を担う世代をターゲットに、農薬の大切さを伝えることは、持続可能な食や農業においても重要です。当社の事業を理解していただく取り組みは、今後も続けてまいります。
生産者や取引先、協力機関、従業員、投資家、地域社会に至る全てのステークホルダーの皆様との対話は、安全・安心で豊かな社会の実現において欠かせないプロセスです。皆様の信頼と期待に応えられるよう、企業価値の向上に全力を尽くしてまいります。